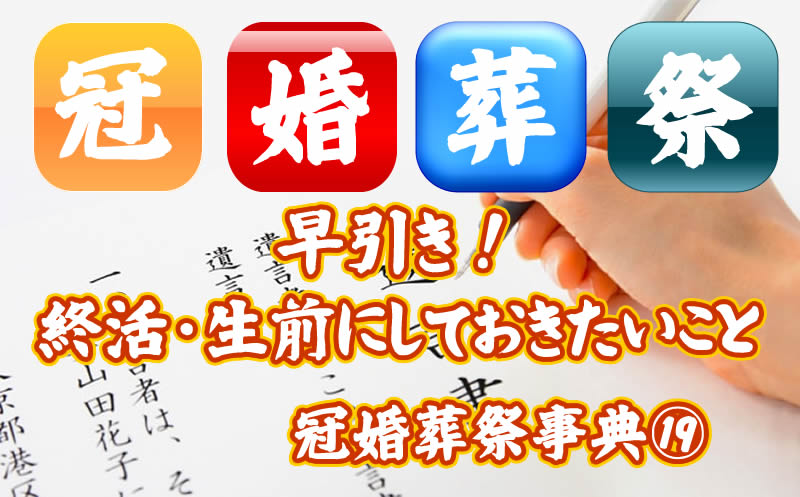
目次 Contents
遺言を準備する
遺言には効力があるものとないものがある
遺言は万能ではありません。法律が守ってくれる遺言の内容は、次の通りです。
- 財産に関すること
- 相続人の排除
- 子どもの認知
- 後見人の指定
- 遺言施行者の指定
- 祭祀承継者の指定
さらに絶対的な施行を望むなら、法にしたがった記しかたをする必要があります。法的に認められている遺言の形は、普通方式と特別方式の2種類で、普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
トラブルになりがちなのが遺産問題です。特に子どもがいない場合、相続権のない義理の娘(嫁)や内縁の妻に残したい場合、相続人がいない場合などは、意思を残すようにしましょう。
|
[普通方式の遺言の種類]
|
遺言ノートは、家族に伝えたいことやメッセージなどが1冊にまとめられます。法的な拘束力はありませんが、遺族にとって心の支えとなるでしょう。
メモ 音声や画像は無効
CDやDVDに遺言を残す人がいますが、実は、この方法は法的に無効なのです。なぜなら遺言は、それが本人のものとわかることが必要だからです。
肉声が入ったCDやDVDは、一見、これ以上の証拠がないように思いがちです。しかしこれらは内容の編集が可能で正確さが判断できないということ
から、認められません。
遺言書の文例
自筆は簡単に作成できるが書式違反で無効になることも
自筆証書遺言は、自分で簡単に作成でき、遺言の存在や内容を秘密にすることができるのが長所の一方、書式違反や内容不明があると無効になってしまいます。自筆で書く場合は、その点に気をつけながらルールにしたがって書きます。証人は不要ですが、紛失や隠匿を防ぐために、保管場所を信頼できる第三者に伝えておくとよいでしょう。
|
[自筆証書遺言の文例] 遺言書 遺言者○○○○、この遺言書により次のとおりに遺言する。 1 遺言者は妻○○に次の財産を相続させる。 この遺言書は遺言者○○○○が全文を自筆し、日付および氏名を書き、自ら捺印した。 |
自筆証書遺言のポイント
- 代筆やワープロなどは無効なので、すべて自分で記入する。
- 作成年月日を記入する。
- 署名、捺印(できれば実印)をする。
メモ 遺言を勝手に開封すると無効になる場合も
封印してある遺言書は必ず家庭裁判所に提出し、正式な手順を踏んで開封します。
遺言書は家庭裁判所で検認を受けることで、効力を持つため、勝手に開封すると、偽造などが疑われ無効になる場合もあります。
家庭裁判所で検認を受けるためには、遺言書の原本、遺言書検認裁判申立諸、遺言者と相続人全員の戸籍謄本が必要です。
遺言の開封は、相続人の立ち会いのもとで行われ、有効であると法的に認められた場合、遺言書の記載の内容にしたがうことになります。
葬儀のスタイルについて考える
希望する葬儀があれば家族に伝えておく
自分で葬儀についての準備を始める場合、まずは、どの宗教にのっとって行うかを考えます。家族や親せきと異なる宗派や無宗教を希望する場合、その理由を家族に話し、納得してもらったうえで理想とする葬儀内容を具体的に伝えておきましょう。費用の準備や喪主の指定、戒名を授けてもらうかどうかなども決めておきたいことです。
また、尊厳死や臓器提供を望む場合は、その旨も話し合っておきます。
「もしものとき」に、親しい人たちに伝えたいことを、エンディングノートにまとめて記入しておくのもよいでしょう。法的拘束力はないものの、終末期や死後のことなどの希望を記せば家族の負担も軽減できます。
ひとり暮らしなら、死後の処理をだれかに頼む
ひとり暮らしの場合、特に家族がいない場合は、死後の処理をだれに頼むかを考えなくてはいけません。信頼できる友人に葬儀や死後の処理を頼んでおくのかよいでしょう。火葬は市区町村でも行ってくれます。また、それ以外に死後の処理を代行してくれる機関もあるので、そこを利用するのも一案です。
メモ 自由葬の希望はくわしく伝える
自由葬を希望する場合は、生前に内容だけでなく進行まで計画し、こんなふうにしたいという内容を、家族に詳しく伝えておくことがたいせつです。
例えば、どんな形式で行いたいのか、だれを呼んでほしいのか、どんな音楽を流してほしいのかなどです。
生前契約や生前予約を扱っている葬儀業者などのプランを利用すれば便利でしょう。
さらに、法的手続きを遺族がスムーズに遂行できるようにしておくのもたいせつです。
生前契約、生前予約とは
具体的な葬儀内容を決める「生前契約」と「生前予約」
最近、自分の葬儀スタイルは、自分で決めておきたいという人が増えています。そうしたニーズに応えて、「生前契約」と「生前予約」で、あらかじめ具体的な葬儀内容を決めることができるようになっています。
生前契約では、葬儀の内容や料金の支払い方法を明確にして契約書を交わすため、確実に希望の葬儀が実現可能です。葬儀だけでなく、墓の手続きや、死後の各種届け出まで請け負う業者もあります。一方の生前予約は、計画を立てておくまで。生前契約ほどの厳密さはないのですが、その分、柔軟性があり、かえって利用しやすいようです。
どちらの方法にしろ、ほとんどの場合は家族の同意が必要です。きちんと、話し合ったうえで決めるようにしましょう。
費用のプランニングも生前に行うと安心
生前契約や生前予約をしても、生前に費用を支払うことはありませんが、葬儀の内容とともに、葬儀費用をどう支払うのかを計画しておくと、希望にそった葬儀を実現しやすくなります。特に自由なスタイルや、予算がかかる葬儀の場合は、決めておかないと計画通りの実現がむずかしくなることもあるでしょう。
|
[生前予約の流れ] ※全葬連による相互扶助システム「if共済会」の例
|
冠婚葬祭早引き事典シリーズ
① 教えて 祝儀袋の表書き
② 喜ばれる 中元・歳暮の贈り方
③ バッチリ決める!訪問のマナー
④ 大切なお客様の おもてなし
⑤ おいしくいただくテーブルマナー
⑥ 『手紙の書き方』これで解決!
⑦ これで安心!結婚式に招待されたら!
⑧ 仲人を頼まれたら
⑨ 婚約・結納のしきたり
⑩ 結婚披露宴のプランニング
⑪ 結婚式挙式のプランニング
⑫ 出産から成人まで!わが子のお祝いごと
⑬ 大切にしたい人生の記念日・お祝いごと
⑭ 暮らしの歳時記
⑮ お葬式参列のしきたり
⑯ ご臨終!突然「遺族」になったら
⑰ 仏式のお通夜・お葬式
⑱ 神式・キリスト教式のお葬式
⑲ 終活・生前にしておきたいこと
⑳ お葬式 Q&A よくあるご質問
㉑ お葬式が終わってからのこと
㉒ お墓と納骨のこと
㉓ 四十九日・年忌法要の行い方
最新情報をお届けします
Twitter で「がばいはやぶさ」をフォローしよう!
Follow @gabaihayabusaコメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)


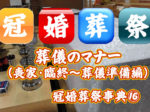


この記事へのコメントはありません。